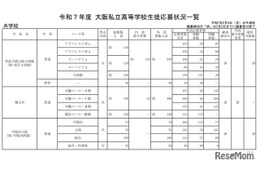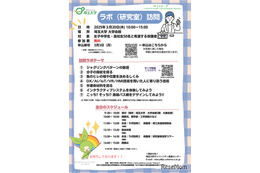どうすれば成績が上がるのか、多くの人にとってもっとも悩ましいのが「国語」ではないだろうか。リセマム編集部では今年の中学受験の「国語」で複数の学校に採用された書籍を紹介したが、実際に問題を解いてみると、大人でも考え込むような設問に直面することも多いだろう。
「国語」でさらにハードルが上がるのが「詩」の問題だ。「詩」を出すと学校として有名なのは、日本最難関の灘中学校と筑波大附属駒場中学校。本日(2月5日)、まさに合格発表のあった筑駒の問題がSNSで話題になっている。
この詩の作者である東田直樹氏は、13歳の時に執筆した『自閉症の僕が跳びはねる理由』が30か国以上で翻訳される世界的ベストセラーとなり、その後も『自閉症の僕が跳びはねる理由2』『ありがとうは僕の耳にこだまする』『あるがままに自閉症です』『跳びはねる思考』『自閉症の僕の七転び八起き』『自閉症のうた』などの多数の著書がある。2021年10月には、『Forbes JAPAN』誌が選ぶ、世界を変える30歳未満の30人(30 UNDER 30 JAPAN 2021)に選出され、昨年6月に最新刊『自閉症の僕の毎日』(KADOKAWA)が出版された。
なぜ、日本最難関の中学入試で、あえて「詩」が出題されるのか。
中学受験塾スタジオキャンパス代表で国語の講師としても教壇に立ち、『令和の中学受験』(講談社)、『ぼくのかんがえた「さいきょう」の中学受験』(祥伝社)、『親の語彙力』(KADOKAWA)などの著書がある矢野耕平先生はリセマム編集部に次のようなコメントを寄せてくれた。
【矢野耕平先生のコメント】
「読解力」とは「文章を『読』んで、『解』くこと」ではありません。「文章を『読』んで、理『解』すること」です。
多岐にわたる読解スキルのひとつとして、「コノテーション(言外の意味)の理解」が挙げられます。たとえば、比喩表現、暗示表現、アイロニー(反語・皮肉)などがその典型例です。「翔平が部屋にこもってしまったからというものの、外の雨は降りやまなかった」という一文を読んで、「部屋にこもって以降、翔平はゆううつであった」という意味を受け取る、といったものです。私は中学受験で国語を指導していますが、この点の理解度の深浅については子供たちの間で相当な差が認められると感じています。そして、中学入試の読解ではこの能力が試される問題がしばしば盛り込まれます。
最難関校と形容される男子校の灘・筑波大学附属駒場で出題される「詩」は、他校ではほとんど見かけません。ではなぜ出題されるのか。その理由として、私は「詩」こそがこの「コノテーション」スキルがもっとも診断できる分野だからだと考えます。限られた文字列の中に、正解に至るまでの確たる根拠を見出し、作者がことばに「滑りこませている真意」をつかむ。このスキルに秀でている子供たちは間違いなく「高度な読解力」の持ち主だと判定できるでしょう。
ちなみに今年の灘中学校で出題されたのは、三角みづ紀氏の『どこにでもあるケーキ』より「プラネタリウム」という詩。三角氏が自身の思い出を重ねながらひとりの13歳を描いた詩の1篇だ。
受験対策というのをいったん忘れて、まずはじっくりとこうした詩を味わってみるのも良い親子の時間になるのではないだろうか。