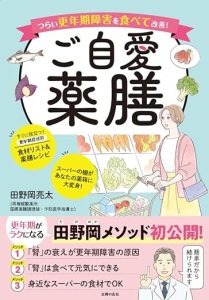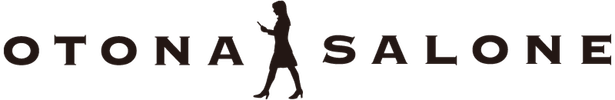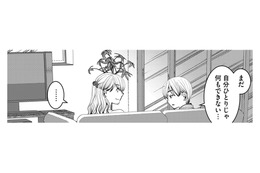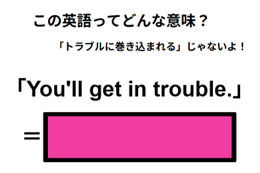こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
たくさんある熊本名物。さつまいもが旬です

11月に入るといよいよ収穫の秋です。先日は通勤路の脇でさつまいも掘りの風景を見かけました。熊本には農産物の名産品が多くありますが、さつまいももその一つです。

熊本には「いきなり団子」という郷土名物があります。輪切りのさつまいもを小麦粉で包んで蒸した素朴なおやつで、熊本空港でも売られています。

「いきなり」とは「簡単・手早く・すぐに」という意味の熊本弁です。短時間で簡単につくることができる、急な来客でもすぐに出せる、というのが名前の由来だそうです。「蒸す」は調理に油を使用しないので、消化作用をする脾の機能にとって優しい調理方法です。改めて考えてみると、調理方法にまでこだわりがつまった郷土料理ですね。
今回も前回同様、旬の食材のありがたさを薬膳・中医学で紐解いてみます。少し難しい説明も含まれますが丁寧に書いてみたいと思います。まず、「さつまいも」です。さつまいもは身体に摂り込まれたらどんな働きをするのか…がこちらになります。
■さつまいも
【補中、益気】自然の“甘み”で脾の機能に働きかけます。
【補腎】肺の呼吸のパートナー“腎”にも働きかけます。
【生津、滑腸、通便】身体に潤いを補い、大便の通りを良くします。
さつまいもは身体に摂り込まれた後、脾と腎の経絡に入るとされています。秋から冬への季節の移り変わりの“変化”の時季の脾の機能には嬉しい働きかけです。呼吸は肺と腎の共同作業と中医学では考えています。秋~冬にかけては、寒さ・乾燥を得意としない肺の機能をケアしてあげたい時季なので、腎への働きかけは肺の呼吸の働きを助けてくれますね。脾と腎の機能に働きかける食べ物がこの時季に最盛期を迎えるのはとても理にかなっていて感心します。
脾の機能の消化作用にさつまいもが働きかけることと、身体の中に潤いを生みだして(=補って)大腸のコンディションを滑らかな良い状態にすることで、大腸と表裏関係の肺の機能にも良い影響があらわれます。さつまいもの名産地であり、郷土料理としてよく目にしていますが、“旬”という視点で改めて見ると、この時季に嬉しい効能を届けてくれる食材と紐解くことができ、自然の恵みに感謝するばかりです。
土用の期間は「変化」の時季。食材にもこの期間に性質が変化するものがあります

霜降の期間は秋から冬への“変化”の時季で、「次の季節に備えて、おなかのコンディションを整えましょう」というメッセージなのですが、“変化”と言えば「性質が変化する食材」があります。ここからはちょっとそのお話を。
■柿
【清熱】身体の深部の熱を冷ます。
【潤肺、生津】身体に潤いを補う。
【止咳】咳や喘息を鎮める。
■干し柿
【潤肺、生津】身体に潤いを補う。
【健脾】脾の機能(=消化機能)を健やかにする。
【利咽】喉の疾患を改善してスッキリさせる。
生の柿は、身体の熱を取り去る「寒(かん)」の性質があるので【清熱】の働きをしますが、干し柿にすると身体を冷ましも温めもしない「平(へい)」の性質に変わります。果肉のみずみずしさと自然の甘みによる【生津(しょうしん/せいしん)】の働きは、身体に摂り込まれた後に身体の中に潤いを生みだす(=補う)ことを意味します。この働きは、表面にできる白い粉の“柿霜(しそう)”という形になって干し柿でも残り続けます。補われた潤いが喉の粘膜の乾燥に働きかけることで【止咳・利咽】という喉の乾燥症状を取り去る働きになります。
つまり柿を干すことで、「身体を冷ます性質」が取り除かれて「身体に潤いを補って、乾燥による喉のトラブルを解消する」という形への変化が起きます。暦が霜降を迎えて、涼燥に包まれた身体は「身体を冷やさずに潤いを補う」ことを求めているので、「生柿から干し柿への効能変化」はまさに身体にとって嬉しい“変化”です。是非、この変化を摂り入れていただきたいと思います。
肺・脾に嬉しい、干し柿と蓮根の二層杏仁豆腐

秋から冬への“変化”の時季におススメの“肺・脾の機能にうれしい食材”で干し柿に続くものとしては、蓮根、杏仁、豆乳、クコ、鶏肉、にんじん、りんごなどが挙がります。
これらの“肺・脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「干し柿と蓮根の二層杏仁豆腐」です。干し柿をそのまま食べる以外で摂り入れる方法を紹介したい想いと、涼燥の時季は「なんといっても杏仁」という想いが一つになってレシピになりました。
作り方は、まず“干し柿寒天”を作ります。干し柿(1個)のヘタを外して、5mm角のさいの目切りにします。鍋に水(400ml)・りんごジュース(100ml)・メイプルシロップ(大さじ2)を入れて、混ぜながら粉寒天(2.5g)を加えて溶かします。この鍋を中火にかけて沸騰させて、2分間混ぜ続けたら火を止めます。粗熱が取れたら25cmパウンドケーキ型に流し入れ、干し柿を加えて分散させる。これを冷蔵庫に入れて4時間以上冷やし固めます。
次に“蓮根杏仁豆腐”を作ります。蓮根(小1個)の皮をむいてすりおろします。鍋に水(200ml)・豆乳(200ml)・水あめ(大さじ2)を入れて、混ぜながら軽く火にかけた後、すりおろし蓮根・杏仁霜(20g)・粉寒天(3g)を加えて混ぜ合せます。この鍋を中火にかけて沸騰させて、2分間混ぜ続けたら火を止めます。粗熱が取れたら“干し柿寒天”の上に重ねて流し入れて4時間以上冷やし固めます。十分に固まったら、型から外して器に盛りつけたら出来上がりです。
蓮根も性質が変わる代表格。「身体を冷やさずにおなかを気遣う」頼もしさ
生柿・干し柿のケースと同じように、「蓮根」も生の状態と加熱した状態では効能・作用が“変化”します。
■蓮根(生)
【清熱、涼血】身体の深部の熱を冷ます。
【潤肺、生津】身体に潤いを補う。
【除煩】心がそわそわ落ち着かない状態を取り除く。
■蓮根(加熱)
【健脾、開胃】脾の機能(=消化機能)を健やかにする。
【止瀉、固精】身体から漏れることを止める。
【補五臓】おなかの臓腑の調和を整える。
生柿・干し柿の時と同様に、生の蓮根は身体の熱を取り去る「寒(かん)」の性質があるので【清熱】の働きをしますが、加熱をすると身体を冷ましも温めもしない「平(へい)」の性質に変わります。また、生の状態では【生津(しょうしん/せいしん)】の働きで、身体の中に潤いを生みだし(=補い)ますが、加熱をするとその働きに代わって食欲を促して消化機能を健やかにする【健脾、開胃】の働きを持つようになります。
つまり、蓮根を加熱することで「身体を冷ます性質」が取り除かれて「身体を冷やすことなく、脾の機能(=消化機能)に働きかける」という形に変化します。身体は秋から冬へ変化していく土用の時季にいます。柿で気遣ったことと同様に、季節に合わせた一つの知恵として、「身体を冷やさずにおなかを気遣う」ために蓮根の“変化”を利用することも是非活用いただければと思います。
りんごは「料理する」のもまたいい。使い勝手のよい素材です

蓮根の効能の変化を活用した2つ目のレシピとして「蓮根と鶏肉のりんご煮」を紹介します。りんごを洗ってそのまま食べる丸かじり、薄い輪切りにするスターカット…など食べ方もいろいろありますが、料理の食材として使ってみても美味しいです。蓮根のホクホク感とりんごのとろっとした食感のコントラストを味わっていただきたいレシピです。
作り方は、鶏もも肉(250~300g)を一口大に切り、酒(大さじ1)・塩(小さじ1/2)で下味をつけます。蓮根は皮をむいて5mm厚の輪切りにした後、ボウルでりんご酢(大さじ1)を加えた酢水に浸します。酢水につけた後、半量をみじん切りにします。にんじんは5mm厚の輪切りにした後、型抜きで花形にして花びら部分に飾り切りを行います。りんごは軸を取り除き、縦8等分にしてさらに横半分に切ります。
フライパンにごま油をひき、下味をつけた鶏もも肉に火を入れます。鶏もも肉の表面に焼き色がついたら、蓮根(輪切り・みじん切りの両方)・にんじんを入れて軽く炒め、しょうゆ(大さじ1)・りんご酢(大さじ2)・きび砂糖(大さじ4)を加えて3分間ほど中火で味をなじませます。次いで、具材が浸る程度の水・りんごを加えて強火で20分ほど煮込みます。液量が半分程度になったら、器に盛りつけて出来上がりです。りんごが煮汁を吸って旨味の塊になるレシピです。
熊本県は蓮根の産地で、同僚から蓮根をもらったことがありました。そのお返しに…ではないのですが、蓮根と鶏肉のりんご煮を作って渡したところ、「りんごをこんな風に使うなんて初めて知った!」と驚かれたことがありました。冬瓜より形は残りますが、煮汁の旨味とりんご本来の甘みと酸味を感じる…なんともいえない味がします。特売のりんごを見つけた時にでも、ちょっと試していただきたいレシピです。

山形でみかけたりんご
最後に少しだけ、りんごの効能について触れておきます。
■りんご
【生津、潤肺】身体に潤いを補う。
【益胃、消食、健脾】脾の機能(=消化機能)を健やかにする。
りんごはこれから収穫量が増えるのでスーパーの青果棚で目にする機会が増えると思いますが、やっぱりこの時季にケアしたい「消化作用の脾胃」「身体に潤いを摂り込む大腸」に働きかけてくれます。“旬”を並べてくれているスーパーは、その時季の“身体を想う薬箱”のように感じます。
秋に旬を迎える食材は、秋にケアをしたい肺・大腸・毛穴に働きかけてくれます。今回は少し難しく話してしまいましたが、スーパーで「あ!旬だな」「この時季の特価!」のPOPを見かけたら、「おなかの薬だな」と思って手に取っていただけると良いと思います。
次回からは冬ですね。
つづき>>>食欲の秋に「食べたくなるもの」には理由がある。栗やきのこに「隠された」意外な健康パワーとは
連載中の「田野岡メソッド」が書籍になりました!
「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?
日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。
田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!