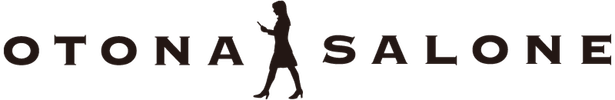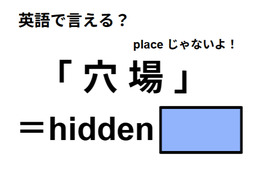更年期症状の代表格、ホットフラッシュ。欧米人に比べれば私たち東アジア人の症状は軽いと言われますが、それでも症状には大きな個人差があります。「満員電車で噴き出す汗が止まらずパニックに。恐怖で電車に乗れなくなり、雇い止めに」「重要なプレゼン時、クライアントの前で紙の資料にぽたぽたと汗が垂れて止まらず、恥ずかしさから自信を喪失して退職」など、人生を大きく左右してしまったという声も聞こえます。
国立長寿医療研究センターと東京科学大・寺内公一教授、アステラス製薬の共同研究によると*1、50‐54歳の4.4%、55‐59歳の2.8%もの女性が「強い」ホットフラッシュを抱えます。強・中・弱すべてを含めた有症率は50-54歳で45.2%、55-59歳で31.7%。50-54歳女性の人口は約474万人ですので*2、重傷者だけでも約20万人、有症者全体ならば約214万人という、想像以上に規模の大きな悩みであることが推測されます。
そんな中、24年ごろから聞こえはじめたのが「新しい治療薬」の朗報。非ホルモン製剤で、ホットフラッシュを抑えることができるらしい……? そこで、女性医学の中でも生殖内分泌がご専門である徳島大学医学部産科婦人科学分野の岩佐武教授にお話を伺いました。
ホットフラッシュはなぜ起きる? 「体温調整のゆとりが極端に狭まるのがその原因です」
――まず、なぜホットフラッシュが起きるのか、その仕組みを教えて下さい。よく自律神経が混乱して起きると説明されますが、それがなぜあの滝汗に結びつくのでしょうか。
はい、ホットフラッシュは大変やっかいですよね。やはりカギは更年期に差しかかって起きる女性ホルモン、エストロゲン量の低下です。閉経が近づき、卵巣機能が低下し、エストロゲンの分泌が減少すると、暑さや冷えを感じやすくなって体温調節に不具合が生じます。これに対する自律神経反応として、ホットフラッシュが起こると考えられています。
――先に体温調節ができなくなって、あとから自律神経が反応しているのでしょうか。ならば衣服でカバーできる要素がある……?
正確に言うと、体温調節中枢の閾値が変化し、その結果として自律神経反応が過剰に出るという感じです。自律神経を「交感神経」と「副交感神経」に分けて考えると分かりやすいかもしれません。交感神経は、車でいうとアクセルのような役割で、活動するときに体を緊張・興奮状態に導きます。一方、副交感神経はブレーキのような役割で、休息やリラックス時に働いて体を休ませます。
更年期になると、自律神経が関わる体温調整の「振り幅」が狭くなるといわれています。エストロゲンが減ることで、「暑すぎる」「寒すぎる」と感じる幅が小さくなり、その変化に体が過敏に反応してしまうのです。結果として「汗を出して体温を下げよう」「血管を広げて熱を逃がそう」という働きが過剰になり、顔のほてりやのぼせ、大量の発汗、いわゆるホットフラッシュが現れます。つまり体温調整の「ゆとり」が狭まることで、体温に関係する症状が出やすくなります。
ホットフラッシュの症状をピンポイントで抑える「ホルモン補充ではない薬」そのメリットとは?
――新薬の成分名は「フェゾリネタント」。ヨーロッパやアメリカでは「ベオーザ」(VEOZA)という名称ですでに使用されています。実は日本のアステラス製薬が開発した薬なのですが、先に海外で認可されました。
ちょっと専門的な話をしますと、本剤は床下部のKNDy(キャンディ)ニューロン群に含まれるNKB(ニューロキニンB)の作用を阻害する仕組みで、「NK3受容体拮抗薬」と呼ばれます。
――国内でもアステラス製薬が2024年に「第相試験」(新薬の承認申請前の最終段階の大規模臨床試験)を開始しており、現在のところ28年ごろに認可されるのではないかと言われているようです。
従来の標準治療であるホルモン補充療法(HRT)は高い有効性を示す一方、血栓症や乳腺組織への影響を考慮しながら慎重に投与する必要がありました。これに対し、「NK3受容体拮抗薬」はホルモン剤ではないため、そうしたリスクを回避しつつ、ホットフラッシュに選択的かつ直接的に作用する治療法として期待されています。
――ホットフラッシュにだけ効く薬ということですね。どうせなら他の症状も治してくれてもと思ってしまったりもしますが、従来の薬と比べて私たち患者にどのようなメリットがあるのでしょうか?
「ホルモン剤ではない」、これが最大にして最高のポイントです。というのも、HRTは血栓やがんなどのリスクも否定できないため、子宮や乳腺に異常がないか定期的に検査しながら行います。従って基本的に産婦人科での管理が必要です。しかし新薬はホルモン剤ではないので、内科など他科でも処方が可能になるのではないでしょうか。もし産婦人科を受信することが「ハードルが高い」と感じる患者さんであれば、かかりつけの内科で「汗を止めたい」と気軽に相談しやすくなるメリットが考えられます。
また、産婦人科でも、血栓や乳がんの既往を持つ患者さんへの治療法が増えるのは嬉しいことです。たとえば、乳がん後の患者さんは女性ホルモン分泌を止める薬を5年から10年服用しますが、わざわざ止めているホルモンの補充はできないため、患者さんが更年期症状を訴えても打つ手が乏しかったのです。NK3受容体拮抗薬の登場でホットフラッシュには対応できるようになります。
「KNDy(キャンディ)ニューロン」と「キスペプチン」の働きとは?
――この薬剤では「KNDy(キャンディ)ニューロン」ともうひとつ「キスペプチン」「という言葉が登場します。どちらもかわいらしい名前で印象的ですが、どのような役割なのでしょうか。
脳の「視床下部」は体温などをコントロールしています。ここには「KNDy(キャンディ)ニューロン」という神経細胞があり、体温調節に重要な役割を果たしています。正常時はエストロゲンがKNDyニューロンの働きを適切にコントロールし、体温のバランスを保っています。ですが、エストロゲンが急減するとコントロールが効かなくなります。
「キスペプチン」は主に生殖機能をコントロールするペプチドです。アクセル役の「ニューロキニンB(NKB)」とブレーキ役の「ダイノルフィン」が「キスペプチン」を調整しています。この3つの頭文字をとった名前が「KNDy(キャンディ)ニューロン」です。
エストロゲンが減少すると「もっと出して」とアクセル役のNKBが過剰に放出され、そのNKBが自身のスイッチである「NK3受容体」を押すことでKNDyニューロンが興奮します。NK3受容体は脳の体温調節中枢にも存在しています。
つまり、過剰に放出されたNKBが体温を調節する神経まで刺激してしまって体温調節のバランスが崩れます。結果「体は暑くないのに暑い」と脳が勘違いしてほてりや発汗が引き起こされるのです。
――Nk3受容体が押されなければキスペプチンが放出されず、体温調節のバランスが崩れないということですね。
はい、KNDyニューロンが過剰に活性化することを抑えれば体温調節は正常になります。「NK3受容体拮抗薬」は受容体の側にくっついてNKBの伝達をブロックするので、信号が体温中枢へ伝わらなくなり、ホットフラッシュを抑えられるという仕組みです。
このキスペプチンの働きは、もともとは「がんの転移を抑える物質」として研究され発見されました。その後、脳内にも存在し、排卵や月経など女性の生殖機能を支える重要な役割を持つことがわかりました。当初は不妊治療など生殖医療の分野で注目されていましたが、仕組みが解明されるに従って更年期女性のホットフラッシュを抑える役割に注目が集まり、治療薬として研究が進んでいるのです。
内科でも処方できるようになるかもしれないのは朗報だが、婦人科での診察も並行してほしい
――婦人科以外で処方できるようになるのはよいことですが、いっぽうで他科で処方してもらう場合に気を付ける点もあるのでしょうか?
婦人科に限らず、近隣で通いやすいクリニックで薬を処方してもらい、症状が軽減するのは喜ばしいことです。ただし一方で、ホットフラッシュの薬を求めて内科を受診した女性が、ホットフラッシュだけでなく何らかの婦人科疾患を抱えていた場合、早期に専門的な検査を受けて発見する機会を逃すリスクもあります。そのため、内科などで薬を処方してもらう場合でも、定期的に婦人科検診を受けるなど、ご自身が更年期という時期に差しかかったことを自覚し、この時期以降に起きやすい疾病についての予防意識を持つことが大切です。
――内科のほうが確かに気楽、これは事実とはいえ、まだまだ「汗くらいで病院に行ってもいいの?」という声も集まります。この点はどうでしょう。
ホットフラッシュは、人によっては日常生活も滞るほど辛いケースもあります。現実に仕事や日常に支障が出ているのであれば、それは治療すべき疾患です。医師の何気ない言葉で傷つく患者さんがいらっしゃるというのは私たちも耳にしますが、仮に医師が「汗くらいで受診するなんて」と口にするようなら、その医師の側に認識を正していただきたいなと感じますし、患者さんもへこたれずにぜひ相性のよい医師を探していただけないかなと思います。
何であれ患者さんが不自由な状態にあるならばそれを正し、元の状態に戻るようにできる限りの手助けを続けるのが医業ですから、必要があれは是非専門の医療機関に足を運んで欲しいです。
つづき>>>更年期に私たちが太る原因、もしや「オキシトシンの減少」も影響してる?意外なつながりを医師に聞く
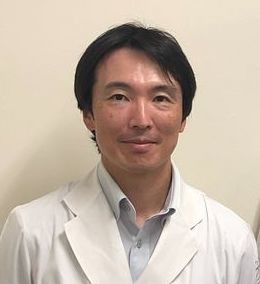
お話/徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学分野 教授 岩佐武先生
産婦人科専門医・指導医、医学博士。2002年徳島大学医学部卒業。同大学病院地域産婦人科診療部特任助教、米カリフォルニア大学バークレー校、徳島大学病院地域産婦人科診療部特任准教授、同周産母子センター講師などを経て、2020年から現職。生殖医療専門医、内分泌代謝科専門医・指導医(産婦人科)、女性ヘルスケア専門医。
*1 Tomida M.et al, Vasomotor symptoms, sleep problems, and depressive symptoms in community-dwelling Japanese women.J Obstet Gynaecol Res.,2021 (PubMed)
*2総務省「人口推計」2025年3月確定値
*3 Samuel Lederman et al, Fezolinetant for treatment of moderate-to-severe vasomotor symptoms associated with menopause (SKYLIGHT 1): a phase 3 randomised controlled study,Lancet,2023 (PubMed)