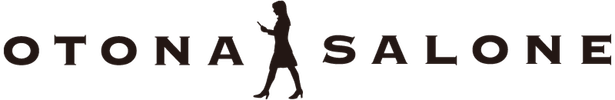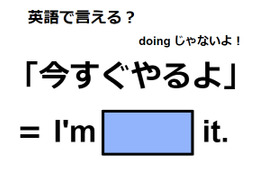*TOP画像/つよ(高岡早紀) 三和(山口森広) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」26話(7月6日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「捨て子」について見ていきましょう。
江戸時代は子どもを「みかん籠」に入れて捨てていた!?
親は子を守り育てるべきという考え方が一般的ですが、すべての親が子を育てられるとは限りません。いかなる者も産んだ責任をもつべしという意見は正論であるものの、時と場によってはきれい事になってしまうのが現実です。
江戸時代において捨て子の存在は町の景色の1つであり、「みかん籠」は捨て子の代名詞でした。蔦重の死から約6年後に出版された『敵討巖間鳳尾艸(かたきうちいわまのかじのき)』(1803年)は武家のお家騒動をテーマにした作品ですが、当時の捨て子に対する考え方がよくあらわれています。家臣は奥女中との間に子を授かるものの、奥女中は産後すぐに亡くなりました。家臣は子を育てられるわけがなく、赤ん坊をみかん籠に入れて、他所の家の前に置きました。現代であれば、自分が生んだ子どもを育てられないからといって、他人の家の前に置くのはありえない話ですが、当時においてはごく普通のことだったようです。
同著では、この家臣は「人が言うように情け深い人だろう。これで、こぞうの命が助かるだろう」と赤ん坊を置いた家の人について述べているし、子を置かれた側も「このような良い子を捨てる親の心は思い遣られる。おれの子にするぞ。泣くなよ」と寛大な心で受け止めています。
また、「べらぼう」においても当時の養子に対する考え方が垣間見れます。吉原を代表する引手茶屋の主である市右衛門(高橋克実)は、蔦重(横浜流星)の商売に対する姿勢と才覚を早くから見抜き、他の子は手放しても、蔦重は自分のもとに残していました。市右衛門のように引き取った養子に将来性を感じられれば、血のつながりはなくても家を安心して託せました。
とはいえ、江戸時代における捨て子事情は『敵討巖間鳳尾艸』や『べらぼう』の蔦重のような良心的な話ばかりではありません。親は子をお寺の門前に置き去りにし、誰かに育てられることを願うことがありました。しかし、野犬に食べられるなど、悲惨な結果になるケースも少なくなかったといわれています。当時、置き去りにされた幼子が野犬に襲われることは広く知られていました。親は子が野犬のエサになる可能性があることを認識していたでしょう。それでも、貧困や社会的事情により、こうした選択を余儀なくされたのです。
江戸時代においても子どもを捨ててよいわけではなかった
江戸時代について、高齢者や子どもなど生産性のない家族を山や道に平然と捨てていたという先入観を抱きがちです。しかし、子どもを育てられないからといって捨てることが公に認められていたわけではありません。
1687年、徳川綱吉によって「生類憐みの令」が発布され、多くのどうぶつの命を重んじるムーブメントが広がったことはよく知られています。この令はどうぶつのみならず、高齢者や子どももまた憐れみの対象としています。例えば、この令では捨て子の届け出の提出を各地に命じていますし、町に対して捨て子の保護を義務付ける命令文もあります。
また、蔦重の時代の『御定書』(1742)では「金を付捨子を貰其子を捨候者 引廻獄門」と定められており、お金を払って買った子を捨てた場合、公開処刑(引き回し)の対象となりました。
庶民の子どもは10歳未満で働きに出る
江戸時代において、庶民の子どもの多くは10歳前後で奉公に出されました。貧困層の中には5歳前後の子どもを奉公に出す家庭もあったといいます。
奉公先では丁稚から始まり、年季が明けると職人と対等の身分を得られました。奉公人の労働時間は12時間ともいわれており、長時間労働を強いられました。奉公というと聞こえはよいですが、実情は我が子を金銭と引き換えに下働きとして差し出すことに他ならなかったようです。
なお、女子の場合は子守りや各家庭の下働きとして、経済力がある家に働きに出されました。また、借金がある家では幼い我が娘を吉原に売る選択を強いられることもありました。吉原では10歳前後で売られた禿という少女たちが上級遊女の世話をしたり、遊女になるための指導を受けたりしていました。
本編では、江戸時代の「みかん籠」に入れて捨てられた子どもたちの悲しい運命や、幼くして奉公に出される庶民の子どもたちの過酷な現実をお伝えしました。
▶▶鬱々とした世の中だからこそ、江戸の“家族”観を超えていく。蔦重とてい、そして母との再会が描く「本当の絆」とは?【NHK大河『べらぼう』第26回】
では、蔦重とてい、そして母との再会を通じて描かれる「本当の家族の絆」について深掘りします。
参考資料
沢山美果子『江戸の乳と子ども -いのちをつなぐ-』吉川弘文館 2016年
深谷大『さし絵で楽しむ江戸のくらし』平凡社 2019年
畠山健二『超入門! 江戸を楽しむ古典落語』PHP研究所 2017年
パオロ・マッツァリ『歴史の「普通」ってなんですか?』 ベストセラーズ 2018年