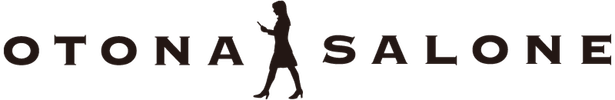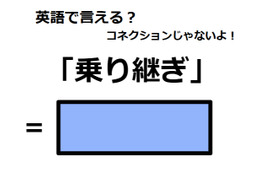*TOP画像/喜右衛門(風間俊介) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」20話(5月25日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「丁髷(ちょんまげ)」について見ていきましょう。
江戸時代における男性のトレードマークといえば「丁髷」
丁髷という言葉は江戸時代に生まれましたが、前頭部から頭頂部にかけて半月形に剃る月代(さかやき)は鎌倉時代に始まり、武士が兜による頭の蒸れを防ぐために考案された髪型です。
江戸時代には武士が多くいたことなどから、庶民の間でも丁髷が流行りました。丁髷にはいくつかの種類がありますが、蔦重の時代は本多髷(ほんだまげ)という丁髷がスタンダードでした。本多髷は束ねた髪の先を短くするのがポイントです。
ただし、本作においても源内(安田顕)や新之助(井之脇海)は前頭部から頭頂部にかけても髪の毛があります。学者や浪人は総髪を束ねるだけの茶せん髷が一般的であったためです。

源内(安田顕) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」 16話(4月20日放送)より(C)NHK
江戸時代にも髪結い床(=床屋)は数多く存在し、男たちは髪結い床で結ってもらっていました。現代にもカリスマ美容師がいますが、当時も人気の髪結がおり、その手に結ってもらおうと、長時間順番を待つ者もいました。
私たちから見ると、丁髷はどれも同じように見え、違いが分かりにくいですよね。しかし、江戸っ子たちは丁髷にこだわっており、月代の幅や範囲、髷の太さ、長さ、傾斜角度に気を使っていたのです。
ちなみに、現代人も髭などのムダ毛ケアはほぼ毎日欠かせませんが、半円形に剃り落とした部分もすぐに毛が目立つほど伸びるため、当時の人たちは月代を美しく保つために手間がかかったといいます。一部の職業に従事しているか病気でない限り、頭部のお手入れはマストでした。
また、江戸の男たちは丁髷をした状態で寝ていました。毎日セットしてもらうとなれば時間もお金もかかって大変です。箱枕という高さがある枕をあてて寝ていたため崩れなかったそう。ちなみに、当時の人たちが髪を洗う頻度は月に2~3回程度でした。
蔦重が見てみたいと思った100年後の丁髷…意外な結果にびっくり!?

春町(岡山天音)が考えた100年後の髷 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」20話(5月25日放送)より(C)NHK
本作の第19回で、蔦重(横浜流星)が春町(岡山天音)の手土産にする案思を唐丸(染谷将太)や喜三二(平沢常富)とアイデアを出し合うシーンがありました。蔦重は「100年先の髷って どうなってるか見てみたくねえっすか?」と問いかけ、みんなが「それだ~!」と笑っていましたね。蔦重がこの発言をした100年後、丁髷はどうなっていたのでしょうか…。
南畝の『菊寿草』における『見徳一炊夢』の評価などから考えるに、本放送は1780年頃を描いていると考えられるでしょう(蔦重はアラサー世代)。1780年と仮定すると、100年後は1880年です。目をキラキラ輝かせて、100年先の丁髷を想像していた蔦重ですが、丁髷は一般的な髪型ではなくなっていました。
1871年、明治政府の近代化政策により「散髪脱刀令」(断髪令)が発布されました。この令をきっかけに、丁髷をする人は減っていきました。都市部では短髪が急速に普及したものの、地方に住む人や伝統を重んじる人などは丁髷をつらぬいていました。街には丁髷の人もいれば、短髪の人もいる時代がしばらく続いたのです。また、1833年に生まれた明治時代初期の木戸孝允の写真には丁髷姿とざんぎり頭姿のものがありますが、彼のように二通りの髪型を経験した男性も多くいました。
トレンドに敏感で、新しいものが好きで、時代の流れに順応できる蔦重のことですから、100年後の世界に生きていたら早々にざんぎり頭にしていたかもしれませんね。
ちなみに、蔦重の時代から100年後、首都は京都から東京(1868年9月、江戸から東京に改称された)になり、新橋から横浜間で鉄道が開通し、ガス灯も日本に入ってきました。蔦重がいう100年先の江戸を私たちは知っているからこそ、春町がどのような江戸を想像したのか気になりますね。
本編では、江戸時代の男たちのこだわり「丁髷」文化と、蔦重たちが夢見た“100年先の江戸”の姿をお届けしました。
▶▶いよいよ「天下取り」目前。ビジネスマンとして強気の蔦重、狂歌でまさかの赤っ恥!【NHK大河『べらぼう』第20回】
では、“天下取り”を狙う蔦重のビジネス戦略と、文化人・南畝との出会いが描かれます。意外にも不器用な一面が見えた、狂歌デビューの行方にも注目です。
参考資料
江戸歴史研究会『ビジュアル版 江戸の町と暮らしがわかる本―この一冊で時代小説・ドラマ・映画がもっと楽しめる!』メイツ出版 2011年
小沢詠美子『「もしも?」の図鑑 江戸時代の暮らし方』実業之日本社 2013年
ミニマル、BROCKBUSTER『イラストでよくわかる 江戸時代の本』彩図社 2020年