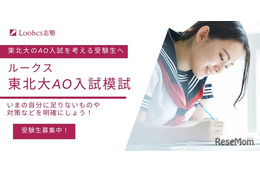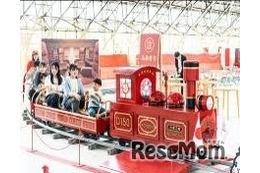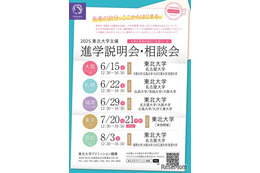本企画では、教育におけるリーディングカンパニーの若手社員に、就職活動当時の思い出、入社後の働き方、これからのキャリアビジョンなどについてインタビュー。教えるだけにとどまらない教育・EdTech業界の魅力を伝えていく。
今回話を聞いたのは、角川ドワンゴ学園でN高等学校・S高等学校・R高等学校の通学コースの生徒たちをサポートする田谷ひかり氏。入社10年に満たない若手ながらキャンパス長を務める彼女の姿から、角川ドワンゴ学園が提供する新しい教育の魅力が見えてくる。
※所属・役職は2025年3月取材時点のもの
未来を担う生徒とともに成長する喜び
--お名前とご所属を教えてください。
角川ドワンゴ学園N高等学校・S高等学校・R高等学校の通学コース運営部に所属し、千葉キャンパスのキャンパス長を務めています。田谷ひかりと申します。現在、約200名の生徒が学ぶ千葉キャンパスの責任者として働いています。
 --入社年と社歴を教えてください。
--入社年と社歴を教えてください。2018年4月に入社しました。最初の3年間はスクーリング運営とメンター業務に携わり、単位認定に必要な授業の運営などを担当していました。2021年4月からは現在の通学コース運営部に異動し、その後、千葉キャンパスのキャンパス長の職に就きました。
--現在の仕事内容を教えてください。
キャンパス長の業務は、生徒たちが必要な単位を取得できているか、進路計画に沿った学びができているかなど、生徒それぞれの学びの確認から、キャンパス全体の運営状況の把握まで多岐に渡ります。とりわけ私は管理業務だけではなく、自ら一部の生徒を担当し、面談を行うなど、積極的に生徒と関わることを大切にしています。
--学生時代に在籍していた学部学科、研究テーマを教えてください。
文学部の英語文学文化を専攻し、1980年代から90年代のアメリカ文化や文学をテーマに学びました。
英語が好きだった私ですが、英語に苦手意識を感じた時期がありました。その際に、これまでと違う先生にアドバイスをもらったところ、その先生のおかげで苦手意識がすっかり払拭できたんです。学びにおける先生の役割の大きさや、先生と生徒との関係性が学習に与える影響の大きさに興味をもち、教職課程を履修することにしました。
--就職活動中、志望企業とどのような接点をもちましたか。
就職活動中は、公立高校の採用説明会に行ったり、採用試験の勉強をしながら、6月に開催される大規模な企業合同説明会にも参加していました。公立学校で働くイメージが掴めず迷い続けていたとき、大学4年生の10月に参加した私立学校の合同説明会で、初めてN高と出会いました。当時の私はN高の名前すら知りませんでしたが、その教育方針に強く惹かれ、これまで迷っていた教職に「この学校で就きたい」と思ったのを覚えています。
 「もし自分が高校生だったら、ここで学びたい」
「もし自分が高校生だったら、ここで学びたい」--「ここで働きたい」と角川ドワンゴ学園を志望するようになった、具体的な理由を教えていただけますか。
所属していた文学部の先輩は幅広い進路を歩んでいて、その分就職先の選択肢は多く感じられましたが、なんとなく周りに流されるままに就職することになってしまうのではないかと戸惑うことが多々ありました。一方で、教職課程を履修したことで教育学部の友人と話すことも多く、「教育」という広い視野で物事を見ることに面白さを感じていました。将来、教育に携わる仕事に就いてみたい。そしてその際には、教科指導だけでなく、生徒ひとりひとりの将来に向き合う進路指導にもっと関わりたい。
就職活動中の自分自身の葛藤の原因を考えたとき、自分自身の高校時代、将来について先生とゆっくり話す時間がなく、進路やキャリアについてじっくり考える機会がなかったことも起因しているように感じられたからです。高校生のうちにそうした時間をもっておくことで、覚悟をもった進路選択ができるようになるのではないか、と。そんな思いを抱えていたとき、説明会で角川ドワンゴ学園に出会い、「私がやりたいことができるのはここだ」と確信しました。
中でも説明会での「世の中の役に立つ教育」という言葉が印象に残っています。また、「もし自分が高校生だったら、ここで学びたい」と思えたことも大きな決め手になりました。
その後も実際に生徒の活動状況をみて「高校生でこんなことをしているのがすごい」と感じました。多様化する社会の中で、未来を担う子供たちにとって新しい選択肢になると考え、私もここで貢献したいと強く思ったんです。
 ジョブローテーションで継続的に成長の機会が得られる
ジョブローテーションで継続的に成長の機会が得られる--入社前の印象や情報のうち、入社後も変わっていないことを教えてください。
学園が掲げている理念は、ネットコースでの単位取得に関わる仕事にも、現在の通学コースで課題解決型授業を運営する仕事にも通底しています。生徒に、社会に出て役立つ武器を身に付けてもらうという根本的な目標は、部署や役割が変わっても変わりません。
--一方、入社後変わったことはありましたか。
年度ごとに授業内容がアップデートされるなど、改善が常に行われています。また、入社当時はなかったジョブローテーション制度が導入され、さまざまな部署で経験を積む機会が増えました。
「教員は社会のことを知らない」という印象をもたれがちですが、ジョブローテーションを通してさまざまな仕事を経験することで、自分自身の引き出しや視野を広げることができています。挑戦する場所をいただけていることに感謝しています。
--若手社員の皆さんの働き方について教えてください。
入社直後から実践的な環境で学ぶスタイルが特徴です。入社時からOJTで先輩が1対1でついてくださり、すぐに実務に当たりました。4月に年度が始まり、入社と同時に新学期が始まるため、座学だけでなく実践を通して学ぶ環境です。ジョブローテーションで違う部署の業務に触れると、同じ学園でも仕事内容が大きく異なることがわかります。常に新しいことを学び続ける姿勢が求められますが、質問しやすい環境が整っているので、安心して働けます。
--私生活と仕事のバランスはどのようにとっているのでしょうか。
私生活と仕事は分けるようにしていますが、緩く繋がっている部分もありますね。自分の引き出しが多いほど、さまざまな生徒との対話に役立ちます。生活と仕事を分けつつも、同じ趣味があれば面談のアイスブレイクになったり、逆に生徒から聞いた話題を自分で調べて新しい趣味になったりすることもあります。
通学コースでは8:30から17:30が基本の勤務時間で、繁忙期でも残業は1時間から1時間半程度です。大学生のティーチングアシスタントが担当する授業の時間に、メンターは面談や成績処理を行うなど、効率的な業務分担が工夫されていますので、プライベートの時間もしっかり確保できます。
--御社の先輩・同期・後輩に、尊敬できる人・憧れの人はいますか。また、どういった点を尊敬されていますか。
所属の部署の部長である沖田さんは憧れです。部長という忙しい立場でありながら、マラソンに挑戦したり、大学院で学んだりと、常に新しいことに挑戦されています。部長が挑戦している姿を見ると、私も何か新しいことにチャレンジしようという気持ちになります。仕事だけでなくさまざまなことに取り組まないと、視野が狭くなり、固定観念に縛られてしまうと思うんです。
--現在の仕事でもっとも「楽しい」と感じることを教えてください。
生徒が自分のやりたいことを見つけ、それを実現していく姿を見るのがいちばん嬉しいです。「全然わからない」と悩んでいた生徒を励まし、声をかけているうちに、いつの間にか私より詳しくなっていることもあります。また、卒業シーズンに無事に巣立っていく生徒たちの姿を見ると、「来年も頑張ろう」とあらためて気持ちが引き締まります。生徒の成長や目標達成を間近で見られることが、教育の現場で働く醍醐味だと感じています。
 --これからのキャリアビジョンについて教えてください。
--これからのキャリアビジョンについて教えてください。ジョブローテーション制度が社会人としての成長につながっていると感じています。これからもこの制度を活用して、さまざまな部署で勉強させていただきたいです。学んだことを次の現場で生かし、成長した自分で生徒と関わり、貢献を続けていけたら嬉しいですね。自分の視野を広げることが、結果として生徒の成長につながると考えています。
--御社に関心のある就活生へ、メッセージをお願いします。
角川ドワンゴ学園が運営するN高・S高・R高は、生徒の成長を間近で支えられる学校です。今、教育の選択肢が増えている中で、当学園は生徒にとっても、働く教職員にとっても新しい選択肢になると思います。生徒の成長を一緒に支えていける仲間が増えたら嬉しいです。
※所属・役職は2025年3月取材時点
--ありがとうございました。
インタビューから見えてきた「角川ドワンゴ学園」の魅力
生徒とともに挑戦し、自らも成長し続ける田谷氏の姿勢は、角川ドワンゴ学園の文化そのものを象徴しているといっても過言ではないだろう。入社から約7年で千葉キャンパスのキャンパス長を務める田谷氏の例からもわかるように、年齢に関係なく、能力と意欲があれば大きな責任を任せてもらえる環境がある。
2018年の田谷氏の入社時と比べ、部署数も従業員数も大幅に増加している角川ドワンゴ学園。急成長する組織の中には、定期的な情報交換や研修を通じ全国のキャンパスと連携することで教育の質を高め合う仕組みや、ジョブローテーション制度を通じてさまざまな経験を積むことができる点、また、効率的な業務分担の工夫によってワークライフバランスがとりやすいなど、自分自身も成長できる環境が整っている。
自分の可能性を広げながら、次世代を担う生徒の成長を支える仕事。角川ドワンゴ学園は、学生にとっても教職員にとっても新しい教育の形を実現している。