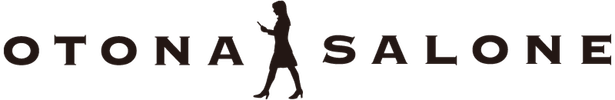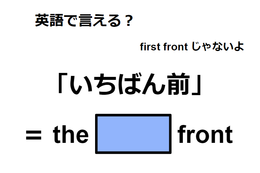今年立て続けに提示された新たな女性のコースモデル、「ローサ型離婚」「アンナ型再婚」。別居をあとに回して籍を外す離婚、病を得たあとでの50代以降の再婚など、従来の結婚離婚の定石ではないスタイルです。法律の専門家からこれらを見る場合、どのような課題や検討点、注意点があるのでしょうか。労働問題を中心に、女性と子どもの権利保全についても活動を続ける伊達有希子弁護士にお話しを伺います。
前編『「ローサ型離婚」「アンナ型再婚」、私たちが取り得る新しい自己決定バリエ。これらが持つ「まだ見えていない法律的な盲点」って?』に続く中編です。
離婚は決して「バラ色の魔法の杖」ではない。「今後の人生設計の緻密なやりなおし」と捉える
華やかな世界を生きる加藤ローサさんの離婚のお話を例に挙げて入りましたが、やっぱり現実に即したミドル世代の離婚の話を伺うと、ものすごくリアルな課題が多数見えてきました。といっても、きっとローサさんも同じようにこうした現実的な問題をたくさん抱えて悩んで人生を選択して、それらの問題をいまも一つ一つ解決していってるのでしょうね。
「そう。みんな苦しんで弁護士に駆け込んで、やがて願いに願った離婚がかないます。どれほど喜ぶかと思うでしょう? ところがみんな泣くんです。どうしてこうなってしまったんだろうと、悲しくて泣くんです。最善の選択をしたはず、添い遂げる未来を考えて結婚したのにと。少したてば元気になるのかもしれませんが、晴れ晴れと帰っていった方は私が担当させていただいた離婚案件で一人くらいしかいません。これがやっぱり現実なんです」
どれだけ長年に渡って心に固く離婚を決めていた人でも、やっぱりメンタルが相当しんどいというのは耳にします。そういうものなんですね。
「そうそう。いろいろな意味で、離婚は一人ではできません。私は必ず最初に『家族やお友達に毎日お電話できますか? 毎日毎日お話を聞いてくれる方っていますか?』と質問しています。穏便に話し合って離婚できる人はいいですが、弁護士を頼るような事態ですともう一人ではメンタルを保つのが無理。こうしてメディアが簡単に離婚離婚言うのは、それもそれで選択肢の多様化を進めるのかもしれないけれど、影ではそういうことが起きてるんです」
その点では、ローサさんの場合は同居を続けたままの離婚のようです。これならば養育費を確実に獲得できますし、住居費用も当面不要、子どもたちも転校等が不要。いずれ家を出る準備を少しずつ進めることができる、とっても賢い方法だなと感じたのですが、どうでしょう?
「同居していても、離婚しているので、もはや配偶者ではありません。なので、男性には法的には扶養義務がありません。生活費、住居費などを支払う義務はなく、当然に経済的に困らないで済むということにはなりません。また、そもそも夫が単身赴任中だとか、家の中での動線が完全に別の二世帯住宅みたいな状態ならばともかく、同居ということはお風呂やトイレも同じところを使うのでしょう? それでも快適に暮らせるのだというならばよいでしょうが、なかなか辛くないでしょうか? 私としては、賢い離婚なんて『ない』というくらいに難しいと思います。元夫が突然家を売ったら出ていかねばならないのですから、結局は退路も確保しないとなりませんし」
なるほど、子に対する養育費と、妻子の扶養義務はまた全然違うのですね、追い出される可能性もあると。しかし、それらを考えたうえでも、未来まで待たずに、ご主人の現役時代の資産を確定させて分与を受けてしまうのは賢い、そんな評価もSNSでは見かけました。
「そう考えれば経済的には賢いかもしれませんね。新しい人生に踏みだせるのですし、ずっと続いたイヤな状態から脱却できるのですから、すべてが悪いことではありません。しかし経済的に有利ならば賢い離婚かというと、私にはそうは思えません。転居ひとつとっても、やはり失うものが大きい。そんな中でみなさん、それぞれの条件での少しでもベターな離婚を探るのです」
なるほど、自分ひとりのことだけならホテルに仮住まいし家探しもできますが、子どもがいるとそうはいかきません。ローサさんも、だからこその同居の維持なのかも。
「離婚は子どもの幸福にとても密接に関連します。親の不和は子どもの不安要素ですし、親の喧嘩が子どものメンタルに与える影響はものすごく大きい。かといって、子どもがいるから離婚できないかというと、それも違います。怒鳴り合いが日常、ましてやDVを受けているなら、やはり子どものために逃げないとなりません。暴力を日常のものとして子どもを育ててしまうと、子どもも暴力に抵抗しなくなるという負の連鎖が起きかねません」
「アンナ型再婚」にはリスクはないのか?「夢のようなケース」を考えてみた場合
いっぽうで、この5月に突如再婚を発表した梅宮アンナさんのケースについても伺います。これもまた、私たちにとっては希望の星といいますか、昨年8月から乳がんの治療を公表していたアンナさんが50代で再婚したことで、我々は「もしかして、50代の私たちもまだ再婚できるんだ?」という夢を見せてもらいました。
「そりゃもう、夢は見てもいいけど、まず現実を踏まえてから夢を見ないと(笑)。私は、特に高齢者の結婚時には夫婦財産契約を締結すること、または遺言(いごん)を書くことをおすすめしています」
もちろん、アンナさんの再婚は彼女の魅力あってのことだとはみんな理解しています。たとえば、2009年アメリカの研究では、AYA世代で妻ががんなど重い病気を患った場合の離婚・別居率は 20.8 %、対して夫が患者の場合は 2.9 % と、乱暴に言えば「夫が重病の妻を見捨てる割合」が約7倍高いことが報告されました。なのに病身の妻と添い遂げようとする男性が新たに現れるとは。
「ですが年齢が上がるほど病を得た男性も増えるので、病ありきの結婚もじゅうぶん考えられる世代ですね。お二人ともお子さんがすでに独立してる点も大きいですよね。お互い自分のことだけを考えられる人生ステージに入って、自分の病気、自分の生き方を真剣に考えた結果、出会うべくして闘病経験を持つお二人が出会ったのではと思います。自分はいま人生のどんな段階にいて、どういう選択ができるのか、自分で自分の人生をどう成り立たせられるのか。こうしたことを冷静に考えられるのは50代以降なのかもしれません」
前編の離婚の話に比べ、結婚となるとお金回りのことはあまり気にせずに、ただ生活を一緒にしていく感じでいいのでしょうか。それとも何かトラブルが起きたりする要素があるのでしょうか。
「生活費用の分担、また財産をどうするかですが、この年代ですとある程度、自分の資産が形成されていることが多いと思います。万が一再び離婚となった場合には、結婚するまでの財産は分与の対象にならず、婚姻後に一緒に作った財産だけが財産分与の対象となりますので、自分が結婚前に形成した資産を財産分与することにはなりません。しかし、どちらかが先に世を去る場合の相続については、相手の財産すべてが対象となります。ですから遺言によって誰に相続させるのかの意思表示をしておく必要があると思います。弁護士としては、離婚や再婚を考える人も考えない人も、60代に差しかかったら遺言(いごん)を書いてみることをお勧めします」
いごん。ゆいごんとは違うのでしょうか?
「同じです。遺言がないと財産を分けたくない法定相続人にも分けねばならなくなります。もっとも、遺留分といって、遺言があっても法定相続人が主張をすれば法定相続分の一定割合を受ける権利があります。でも、遺言があれば法定相続分までは遺産をあげたくない人にあげなくてよい、すなわち自分の財産を分けたくない法定相続人に少ない額しか分けなくてよいことになります」
なるほど、たとえば私が再婚したいと思う相手がある程度の資産を持っている場合、向こうのご家族に「遺産狙いじゃないの」なんて疑われずに済むように、最初から書いておいてもらうという感じでしょうか。
「それもありますね。そして、遺留分は法定相続人の意思が重要視されており、法定相続人が主張しなければそのまま遺言のとおりに亡くなられた方の意向が反映されるので、たとえば、新たに結婚した夫ではなく娘にすべての財産を譲りたいと遺言している場合、新たな夫が遺留分を主張しなければ、その人の財産はすべて娘に譲られます。遺言がないと相続財産の分割協議をしないとならなくなり、ひと手間かかるのです。相続人の手間を減らすことも優しさのひとつとも言えると思います」
なるほど、よくわかりました。それはたとえば日記に書いたり、終活ノートみたいなものに書くのでもいいのでしょうか。
「遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言と3つの種類がありますが、公正証書遺言がもっとも確実性が高いのでおススメです。公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を伝えて公証人が作成するので紛失や儀損ということはほほありえず有効性が認められます。どのようにすればいいかは、お近くの公証役場に相談すればよいですし、弁護士が作成のお手伝いをして公証役場に立ち会うこともできます」
公証役場ってまったくなじみがないのですが、試しに検索してみたら、私が住んでいる東京都世田谷区ですと三軒茶屋にありました。(東京都の場合はこちらから)
「遺言はどう自分の財産を引きつぐかの意思表示なので、私は、50代以降の結婚においては、遺言の作成まで考えた方がよいと思います。本来、遺言は結婚離婚に関わらずみんな作成したほうがよいと思います。うちは一族仲よしでモメないから、モメるほど財産がないからという場合も、自分がどう死んでいきたいかを自分で決める自己決定ですから、いちど考えるといいんじゃないかと思います」
つづき>>>ペアローンで家を買っている人、離婚を考えているなら知っておいたほうがいいことがあります。これからローンを組むときにも注意が必要