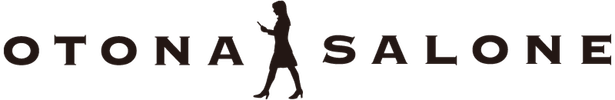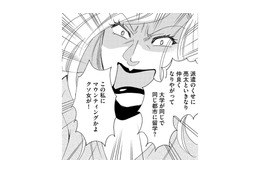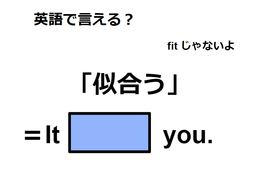大学受験において、基本的には不合格にならない「指定校推薦」。確実かつ安心な受験方法だと思いませんか? ところが高校によっては、生徒にあまり積極的にはすすめないのだそう。一体なぜ!?
親世代の大学受験常識は、もはや通用しない時代。今や大学入試の6割が「推薦入試」と言われますが、情報を入手するのがかなり難しい! 一体、どう対策したらよいのでしょう?
今回は受験ジャーナリスト・杉浦由美子 さんの著書から、大学入試における「指定校推薦」をテーマにお届けしたいと思います。
※この記事は『』杉浦由美子 ・著
推薦入学者の多くは、実は「指定校推薦」。指定校推薦枠なら、ほぼ確実に合格できる
大学の推薦入試のメインは実は指定校推薦です。大学入学者の6割が推薦入試になってきて、総合型選抜や公募制も増えてはきていますが総合型選抜や公募制の何倍もの学生たちが指定校推薦で大学に進学していきます。
この流れは今後もしばらくは続くでしょう。その理由は、総合型選抜や公募制は手間や時間がかかるから、そうそう枠を増やせないのです。
書類審査をして、小論文や面接をするとなると相当な手間がかかりますよね。アメリカではなぜ総合型選抜が中心かというと、アメリカの大学の場合、入試専門の部署に、入試専門職員がおり選抜を行います。つまり、入試業務は専門スタッフが行うから、教授たちは負担が少ないのです。
ところが、日本の大学の場合、入試は大学教授たちの仕事です。最近では優秀な職員を入試課に配置していて彼らが入試業務を担っていますが、それでも教授陣の負担はありますし、大学によっては今でも教授たちが入試業務全般を行っているところもあります。
大学教授というと優雅な仕事だと思われる方もいらっしゃいますが、実際はかなりの激務です。授業の準備、授業、卒論の指導、学生のケア、宣伝活動、事務仕事、それに加えて研究もしなくてはなりません。その忙しい教授たちにとって、もっとも負担が大きい仕事が入試業務です。
まず、一般選抜の入試問題を作るのが大変です。私立大学は学科やコースごとに分けて入試をするところも多く、その分、違う問題を作る必要があるので相当な作業量となります。
一方、指定校推薦は、高校が実質の選抜をしますから大学の負担は少ないです。指定校推薦も志望理由書や学力テスト、小論文、面接などを課しますが、基本、不合格にはしません。
大学と高校の信頼関係の上に成り立つ入試が指定校推薦です。指定校推薦は校内での選抜を通過したら、まず、大学に合格ができます。一部で「指定校推薦でも不合格になるケースがある」ともいわれていますが、データを見た限りは、レアケースです。もし、指定校推薦で希望の大学学部学科に進学できるなら、ぜひ利用したいところです。
「偏差値58~60」が分かれ目! 推薦入試で大学を目指す「推薦校」と、一般選抜志向の「進学校」の違いとは?
指定校を含み、推薦入試に対しては積極的な高校と消極的な高校はきれいに分かれます。あるYouTuberが「偏差値58以上は一般選抜志向で、それ未満は推薦で大学に進学させる方針」と指摘していましたが、取材してみてもその通りです。高校受験偏差値58から60ぐらい、中学受験偏差値だと50できれいに分かれます。
ある保護者は兄弟の上の子が高校受験偏差値60、下の子が偏差値52の高校に通っています。下の子の高校は指定校推薦だけではなく、総合型選抜対策にも積極的です。情報も提供してくれるし、小論文、志望理由書の書き方、そして、面接の対策もしてくれます。
一方で、上の子の高校は、推薦入試には積極的ではなく、生徒が「総合型選抜を受けたい」というと、「準備が大変だからそれよりは一般選抜に向けて勉強をした方がいいよ」と教師が諭します。
偏差値70のある高校の教師もいいます。
「早慶上智やMARCHなどからたくさん指定校推薦がきますが、生徒たちは関心がないですね。MARCHも評定平均値はまず4・0以上はないと出願できませんが、うちで4・0あればMARCHに一般選抜で合格できるんですよ。それなら一般選抜で国立や早慶に挑戦して、併願でMARCHを受けたいと考えるわけです」
ようは学力が高いから、学力で勝負をした方が効率がいいという方針なわけです。一方、生徒の学力がそこまで高くはない高校の場合、学力以外の部分も評価される推薦入試の方が有利になると考えるわけです。
偏差値52のある高校は、一般選抜では早慶上智への合格者はほぼ出ませんが総合型選抜や公募制だと二桁の合格実績を出しています。
ここでは偏差値58以上の一般選抜志向の高校を進学校、偏差値58未満の高校を推薦校と呼びます。
なぜ「偏差値が高くない高校」が、慶應や上智の指定校推薦枠を持っている!?
高校受験や中学受験をする際に、選択が必要となります。進学校か、推薦校か。
「大学に推薦で進学をすることを考えると無理して進学校に入るより、難易度が高くない推薦校を狙う方がいいのでは? 推薦校は評定平均値がとりやすいでしょうし」
と考える親御さんや受験生も出てきます。
推薦校は公式サイトに指定校推薦の一覧を載せていて、大学名学部学科、そして何人の指定校推薦枠がきているかを掲載しています。それを見ると、「この学校で真面目に頑張ればここに載っている大学に行ける!」と思ってしまいそうです。
しかし、推薦校には、指定校推薦を目指して入学してくるライバルが多いので、指定校推薦の校内選考が激戦になっていきます。推薦校はオール5でも希望の大学の指定校推薦がとれないという事態になるケースもあります。
一般大学への推薦も人気がある大学学部学科ですと生徒同士でとりあいになります。ある一般大学の看護科の指定校推薦が1名に対して3人が希望してきて、厳しい戦いになったという話もあります。MARCHの指定校推薦も難易度がなめらかな高校ですと5・0近い評定平均値が求められます。
「上智大学は偏差値40台の高校に指定校推薦を出している」
と揶揄するYouTuberがいましたが、そういうケースの場合、その高校でトップの優等生が指定校推薦をとっていくので、学力的にも人格的にもまったく問題ありません。指定校推薦は、大学と高校の信頼関係の上に成り立つものです。
高校側が模範的な生徒を指定校推薦で大学に送り込みます。その学生が真面目に勉強し良い成績をとってちゃんと就職をしていくと、大学はまたその高校に指定校推薦の枠を出します。
昔より偏差値が下がっている女子校に、今でも慶應義塾大学などの難関大学の指定校推薦がきていますが、それはその高校が長年にわたって、毎年、優秀な学生をその大学に送り出しているから信頼関係が失われないのです。
★【関連記事】では受験ジャーナリスト・杉浦由美子 さんの著書から、推薦入試における「評価平均値」をテーマにご紹介しています。
>>>【「評定平均値 3.5」でも慶應に合格できた!】昭和とは事情が違い過ぎる、いまどきの「推薦入試」。知らないと後悔する大事なこととは?

■著者:杉浦由美子 (すぎうら・ゆみこ)
受験ジャーナリスト。大学卒業後、会社員を経て、2005年から取材と執筆活動を開始。現在は『ダイヤモンド教育ラボ』(ダイヤモンド社)、『東洋経済オンライン』(東洋経済新報社)、『ハナソネ』(毎日新聞社)、『マネーポストWEB』(小学館)で教育と受験をテーマに連載をする。ロングセラー『女子校力』(PHP新書)のほか、『中学受験 やってはいけない塾選び』(青春出版社)など著書多数。