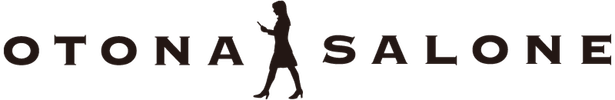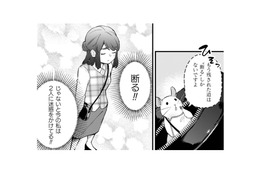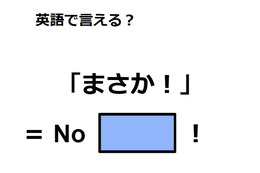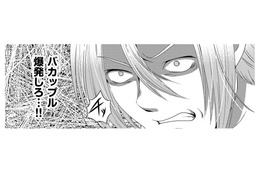*TOP画像/蔦重(横浜流星) てい(橋本愛) 市右衛門(高橋克実) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」39話(10月12日放送)より(C)NHK
「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「蔦重の精神力と江戸っ子の心」について見ていきましょう。
今の時代だからこそ蔦重の“不撓(とう)不屈の精神力”が光る
現代に生きる私たちは自ら人生を切り拓いていくことが困難な世の中に属しています。10代、20代にして現実の厳しさに気付き、人生を半ばあきらめる人も少なくないように思います。
“蔦重”こと蔦屋重三郎は“家なし” “金なし” “親なし”という厳しい境遇にありながら、江戸の町を駆け巡り、30代半ばにして日本橋の店の主人に成り上がりました。商家の下働きの一人にすぎなかったこの男は、鶴屋の主人・喜右衛門(*1)をはじめとする老舗の主人たちと対等な関係を築き、当代随一の絵師や狂歌師たちと親しい関係性を築くまでになったのです。
蔦重は自分の力で耕書道の主に成り上がったものの、店を持ってからも順風満帆ではありませんでした。蔦重がとりわけ窮地に追い込まれた時期は、松平定信が老中首座を務める時期でした。定信は田沼政治の脱却を目指し、江戸の人びとの気を引き締めたため、出版界は出版統制令によって厳しい状況に陥りました。
そうした中でも、蔦重は“おもしれぇものを世に送りたい”という信念を曲げません。いつの時代も、人は政治を皮肉った作品や世相を面白おかしくとらえたものに心惹かれますが、蔦重の時代も同様でした。例えば、朋誠堂喜三二は『文武二道万石通』において幕府の政策や堕落した武士を皮肉りましたが、庶民は普段偉ぶっている彼らの失態や堕落がおかしくてたまりません。蔦重は閉塞感がただよう江戸において、人びとの心の緊張をほぐし、笑いを誘いました。
出版統制が厳しい時期、蔦重は版元や作者名を隠して出版するなどの対策を講じたものの、幕府の目を完全には逃れられませんでした。蔦重の店から出版された山東京伝の洒落本3冊は出版統制の見せしめになり、3冊は絶版、作者の京伝は手鎖50日の処罰を受け、版元である蔦重の処罰については詳細が不明であるものの、財産の半分、もしくは年収の半分が没収されました。
京伝はこの件をきっかけに戯作の世界から距離を置き、教訓本を細々と執筆しながら、煙草の店を銀座で営んだものの、蔦重は屈することなく、作品づくりに精を出し続けました。蔦重は困難な時期においても作品づくりを継続したからこそ、東洲斎写楽が誕生したといっても過言ではないでしょう。
蔦重が幕府の目をかいくぐって書物を出版していたのは、“儲けたい”という思いも単純にあったからだと思います。例えば、京伝のこの三冊についても高い収益を見込めたため、何としてでも出版したかったといわれています。また、京伝側も“おもしろい本をつくりたい”という志だけでなく、生活資金となる原稿料目当てでもあったといわれています(*2)。
蔦重はビジネスマンとして商魂を燃やし、利益を追求しつつも、欲にまみれるのではなく、読者となる人びとの思いやニーズを察し、クリエイターを育成し、人のために動いていました。世を恨み、“成り上がるぞ!”という思いだけで商売を続けていれば、協力者は離れ、誰からも好かれずに失速してしまうでしょう。
蔦重は48歳でこの世を去りますが、彼の亡き後は番頭が店を継いでいます。“ないない尽くし”の蔦重が“江戸のメディア王”に成り上がり、店を守り抜けたのは、人間力や創造力だけでなく、店の主としての強い信念があったからだと思います。
註
*1 蔦重と喜右衛門は親しく、花見に行くほどの仲。
*2 当時、作家に原稿料が支払われることはなかった。作品がヒットした際には遊里での宴会がお礼として催された。喜三二や恋川春町は本業をもっていたため、趣味として作品を執筆していた。一方、京伝は戯作以外の仕事をしておらず、原稿料が特別に支払われていた。
蔦重が耕書堂を存続できたのは江戸っ子の「反抗心」や「欲」にアリ!?
蔦重は書物の取り締まりが厳しい時期を乗り越えましたが、それが叶ったのは”客の存在”があってこそでした。幕府の目をかいくぐって、禁止されている書物を店頭に並べたとしても、それらを購入してくれる客がいなければ利益にはなりませんし、店の経営は立ち行かなくなります。
幕府は春画や好色本の販売を禁じましたが、人間は禁止されたからといって“はい、分かりました。二度と購入しません!”とはならないもの。書物の取り締まりが厳しい時期にも、店と客の間では禁止された書物の取引が裏でひっそり行われていました。
蔦重もまた、秘密を厳守できる客だけを店の奥に呼び、春画をこっそり売っていました。これらの春画は裏での取引になる以上、幕府の検閲の目にさらされることはありません。複雑な彫りが多く、高価な絵の具をふんだんに使った豪華なものでした。さらに、こうした絵は歌麿含む一流の絵師が手掛けていました。
贅沢が禁止されていた世においても、客は高額な支払いをし、豪華な絵をこそこそ購入し、自身の性欲や所有欲を満たしていたのです。幕府が厳しく目を光らせる時期にも、蔦重は幕府の言いつけを破ってでも、欲を満たしたい客がいたからこそ利益を得られました。
ちなみに、定信は“自分には性欲がない”と豪語しており、“性行為は子孫を作るためにするが、情欲はない”と自己分析していたそうですよ。
本編では、“家も金も親もなし”という逆境から成り上がり、出版統制の中でも信念を貫いた蔦重の執念と不撓不屈の精神についてお伝えしました。
▶▶ボコボコにされた蔦重、失神した妻てい。愛と信念と「しなやかさ」で、どこまで波乱を越えられるのか
では、蔦重を支えた母つよと妻ていの姿を通して、家族の愛と逆境に立ち向かう心の力をお届けします。
参考資料
車浮代 『蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人:歌麿にも写楽にも仕掛人がいた!』PHP研究所、2024年
佐藤至子『江戸の出版統制 -弾圧に翻弄された戯作者たち-』吉川弘文館、2017年
三栄『時空旅人 別冊 蔦屋重三郎 ─江戸のメディア王と波乱万丈の生涯─』三栄書房、2025年