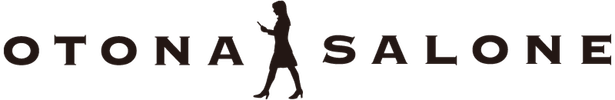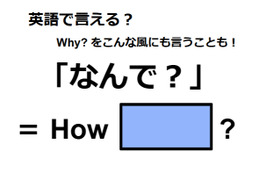こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
夏のピーク!大暑目前、「ちょっとその前の時期」に不眠が多発する理由は
7月19日から夏土用に入り、2025年は7月19日が土用の丑の日になります。2025年は7月31日にも「二の丑」と呼ばれる丑の日があるので、土用に関連する“脾の機能”のお話は大暑の時にさせていただくとして、今回は引き続き小暑の“心の機能”のお話を。
暑い夏の季節は“心(しん)の機能”が活躍したくなる季節です。暑さで汗をかくことが多くなり、身体から透明の液体(=汗)が多く出て行ってしまうと、血液のポンプ機能に負担がかかって心がお疲れ気味になってしまいます。心は、脳をあらわす神(しん)とつながっていると中医学ではイメージします。心に負担がかかってしまうと、神にも影響が及んで安心して眠れなくなる…これも暑い時期に不眠が多くなる要因のひとつです。
暑い夏だけではありませんが、睡眠は身体の中の“心”と“腎”のやりとりが上手に行えるとぐっすり眠れる…と中医学はイメージします。心は身体の中で“陽”の代名詞で太陽のようなイメージ、腎は“陰”の代名詞で湖のようなイメージをします。日中は太陽(心)が輝いているので覚醒していて、睡眠時には太陽(心)が湖の向こうに沈む(=腎に包まれる)ので眠れる…と。
このイメージにおいて「眠りが浅くなってしまう」のは、太陽が盛大になって湖が包みきれなくなるか、太陽は普通ですが湖が干上がってしまって太陽を十分に包むことが出来なくなっているか…です。暑い夏は心(太陽)が活発に働きたくなる季節なので、このバランスを意識してみるのも、眠りが浅くなるなどの“不眠”へのアプローチになるでしょう。
この時期「食べるべきもの」は? 土用には「う」のつくものと言うけれど
暑い夏は“心”の働きが活発になることで、脳をあらわす“神”も穏やかな状態でいられなくなります。眠る時に脳が活性化していると眠れなくなる…のは想像しやすいかと思います。中医学では神を安心させることを“安神(あんじん)”と呼んでいて、安神作用のある食材もあります。
代表的なものに“なつめ”があります。小さいりんごのような見た目の果実で、日本では乾燥させたドライフルーツとして最近よく目にするようになりました。“心”の気と血を補う働きが期待でき、その結果“神”まで穏やかな状態に導かれる…と捉えるとイメージしやすいでしょうか。
他に安神作用が期待できる食材には、最近日本でも目にすることが増えてきた龍眼(りゅうがん)という果物もあります。ライチのような見た目・食感ですが、ライチよりも栄養分が豊富とされていて、中国・台湾では「産後の栄養食材」として有名です。身近な食材で心・神に働きかける作用が期待できるのは……いわし、ピーマン、パプリカ、カカオ、紅茶なども良いです。夏の暑さのもとでお疲れぎみの心の熱を適度に取り除くには、ゴーヤもおススメです。
身体の中で“心と腎のやりとり”が上手に行える、つまり太陽と湖の関係が良好なバランスを保つことが出来るようにするためには、心の機能のコンディションも大切ですが、腎の機能にも目を向けていただきたいです。腎のパワーは、両親からもらった先天的なものの他には「食べる」ことで後天的に補い続けることが大切になります。腎を補う身近な食材としては、山芋、豚肉、えびがおススメです。
心と腎のやりとりに働きかけてくれるのは…ちょっとこの時期「意外」なこの素材

“心と腎のやりとり”に働きかけるおススメレシピを2つ紹介します。1つ目は「3色豚肉巻きの生姜ココアソース焼き」です。身体にこもった湿気と熱を取り去る働きが期待できるいんげんまめ(緑色)、湖で例えた腎の機能を補う働きが期待できる山芋(白色)、心の気血を補って心・神のコンディションを整えてくれるなつめ(赤色)の3色の食材を、身体の気・血・津液すべてを補って腎の機能のコンディションを整える豚肉で巻きました。味付けは、心の気を補う働きが期待できるココアパウダーを生姜・みそと合せたソースを絡めてみました。
作り方は、まず“生姜ココアソース”を作ります。ボウルにみそ(大さじ2)、ココアパウダー(小さじ2)、みりん(大さじ1)、しょうゆ(小さじ1)、きび砂糖(小さじ1/2)、オイスターソース(小さじ1)を入れて、酒(大さじ3)で溶きます。そこに生姜のみじん切り(大さじ1)を入れてよく混ぜ合わせます。
次に豚肉。豚肉(ロース、生姜焼き用)を酒(大さじ1)・すりおろし生姜(大さじ1)で下味をつけます。いんげんまめは軽く下茹でをして2等分にします。山芋は皮をむいて1cm×1cm×4cmの角切りに、なつめは種を外して果肉を細切りにします。豚肉に薄く片栗粉を振り、いんげんまめ・山芋・なつめを乗せて、3色食材を豚肉で巻きます。フライパンにごま油をひいて、豚肉を転がしながら表面に色がつく程度に焼いた後、ソースを加えて中火で5分ほど加熱ししたら完成です。山芋のシャキシャキほくほく感となつめの甘み、ソースの旨味が合わさった初夏におススメのレシピです。

2つ目も身体にこもった熱を取り除きながら“心と腎のやりとり”に働きかけるレシピとして「ゴーヤの佃煮」を紹介します。夏の太陽を浴びてスクスク育ったゴーヤ(苦瓜)は、身体の中にこもった熱を取りのぞく働きが期待できます。佃煮を作る際に、腎の機能を補う働きが期待できるアミえびを一緒に入れました。また、太陽(心)が湖(腎)に向かって移動するときにドロッとした水のよどみ(=痰)があると包まれ効率が下がるとイメージするので、痰を取り除く働きが期待できるみょうがを一緒にしたレシピです。
作り方は、まずゴーヤを縦半分に切って種・ワタを取り5mm程度の薄切りにします。そのゴーヤを鍋に入れて、きび砂糖(大さじ1)、しょうゆ(大さじ2)、みりん(大さじ2)、りんご酢(大さじ2)、水(大さじ3)とアミえび(大さじ1)を入れて沸騰させます。沸騰したら中火にして、汁気がなくなるまで煮ます。火から上げる直前にみょうがを加え、器に盛りつけて白ごまを適量振りかけたら完成です。出来立てのシャキシャキ食感を楽しむことも、1日程度冷蔵庫に置いてなじんだ味を楽しむこともできるレシピです。
もうひとつ質問です。冷房とはどう付き合えばいいですか?
中医学はなんでも陽と陰に分けるので、暑さも“陽暑”と“陰暑”に分けたりします。陽暑は文字通り「熱の暑さ」。陰暑は夏の暑さの中の寒さのことで、「夏ならではの冷えで身体の具合が悪い」「冷たさを求めて身体の具合が悪くなる」のようなことを指します。中医学の歴史は長いのですが、昔の状況でも「暑さを我慢できずに家の外に出て上半身裸で寝ていたら身体が冷えてしまった」ということも症例に挙がっているそうです。
現代の日本だと、冷房やかき氷で身体を冷やす…ということが挙がるでしょうか。最近の日本の夏は熱帯かと思うような気温になりますので、冷房は適度に使用することをおすすめします。ただ、寝ている間にずっと風に当たっている状態だと、起きた時に“しびれ”になることもありますので、冷風が直接身体に当たらないように風向きの調整をしていただけると身体も喜ぶと思います。
夏の疲れは秋に残さないように、心・神の負担を軽減して不眠を回避しましょう。身体にエネルギーを蓄え、眠ることができるように工夫してください。
次回は大暑です。