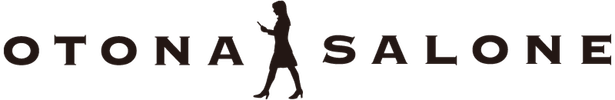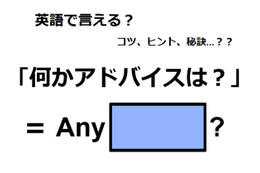写真はイメージです
夫婦問題・モラハラカウンセラーの麻野祐香です。
「夫が家計をすべて管理し、妻に渡すお金を細かく制限。必要な支出ですら『無駄遣いだ』と否定される」
そんなケースは、実は少なくありません。
今回ご相談いただいたFさんのご主人も、まさにそのタイプでした。言葉や態度による直接的な暴力ではなく、お金を使った支配。Fさん自身も最初は「モラハラ」だと気づいていませんでしたが、これは経済的DVにあたります。
※個人が特定されないよう、設定を変えてあります
「夫婦のルール」は、夫だけが決めていた。食費も「許可制」、子どもの文房具も「無駄遣い」?
Fさんの家庭は共働きで、夫は毎月22万円、Fさんは18万円を、夫婦共有の口座に入れる取り決めになっています。
しかし、このルールを決めたのは夫。Fさんは納得していないのに、話し合いの余地もありませんでした。
さらに、その口座を管理しているのも夫だけ。Fさんが自由にお金を使うことはできず、家計は完全に夫の裁量で動いています。
夫は「食費は月5万円まで」と決め、それ以上は夫の“許可”が必要になります。
光熱費や家賃は口座から自動で引き落とされますが、子どもの服や文房具、医療費、日用品など、その都度「買っていいかどうか」を夫に確認しなければなりません。
必要な支出であっても、「それは無駄遣いだ」と却下されることがあるのです。
夫の収入は不明。Fさんの生活はギリギリで
夫は給与明細を見せてくれたことがないため実際の給与は不明で、どれくらい自由になるお金があるのかわかりません。一方でFさんの給与はギリギリで、そこから18万円を共有口座に入れると、自由に使えるお金はほとんど残りません。
夫の許可が下りなかった出費を自分の給与から補填するたびに、Fさんは経済的に追い詰められていきました。それでも夫は「俺のほうが多く負担している」と主張します。実際には、夫のほうが高収入で、趣味や娯楽に自由にお金を使っているようです。
Fさんが「18万円の負担はきつすぎる」と訴えても、「夫婦は平等に家計を負担すべき」「残ったお金は老後のために貯金している」と返されるだけ。手取り収入に応じた割合にしてほしいと伝えても、「これがうちのルールだから」と、取り合ってもらえません。
共働きで収入があるはずの2人なのに、夫だけが経済的に余裕をもち、Fさんは生活に困窮する。この状況こそ、まさに経済的DVにあたります。
妻が「理不尽でも納得してしまう」心理的な理由
ここで疑問に思うのが、Fさんがなぜ「このやり方はおかしい」と強く意見できなかったのか、という点です。それには、いくつもの心理的な要因が複雑に絡み合っています。
● 責められ続けたことで、自己評価が下がっている
Fさんは長年、夫から「無駄遣いだ」「もっとやりくりしろ」と言われ続けてきました。
そうした言葉の積み重ねが、「私はちゃんとできていないのかもしれない」という思い込みにつながり、自己評価を少しずつ下げていきます。その結果、たとえ夫の言い分がおかしいと感じても、「自分が我慢すればいい」と思ってしまい、反論できなくなっていくのです。
● 反論すれば、もっと関係が悪化するかもしれないという恐怖
過去にFさんが夫に言い返した際、夫が無視をしたり、怒鳴ったりといった態度をとったことがありました。そうした経験があると、「何か言えばもっと怖いことが起きるかも」という不安から、自然と沈黙を選ぶようになります。これは「反論=怒られる」という恐怖が無意識に条件づけられている状態です。
● 幼少期から「反論してはいけない」と教えられてきた影響
「親には逆らってはいけない」「黙って従うのが正しい」といった価値観の中で育った人は、大人になっても自分の気持ちを口にすることに強いブレーキがかかります。特に、親が絶対的な存在だった家庭で育った場合、「反論=悪いこと」という感覚が深く染みついてしまうのです。こうした背景があると、たとえ理不尽な扱いを受けても、「自分が間違っているのかもしれない」と感じ、自分を主張することに強い罪悪感や不安を抱いてしまいます。
本編では、共働きで家計を支えているはずのFさんが、なぜ自由にお金を使えないのか。その背景にある“経済的DV”の構造と、心理的支配のメカニズムについてお届けしました。
続く▶▶「『それ、おかしいよ』同僚のひと言で目が覚めた。45歳妻の“反撃”に、夫が動揺した日』」
では、Fさんが自分の違和感を言葉にし始め、夫婦関係に変化をもたらしたプロセスをお伝えします。