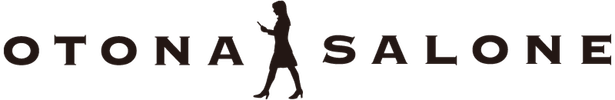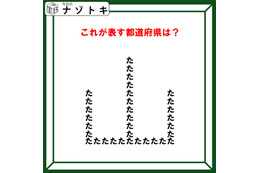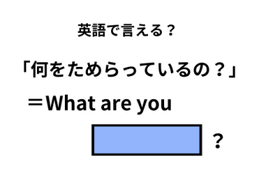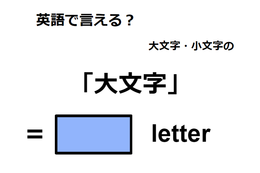日本を代表する食文化の一つであるお寿司。握りたての新鮮なネタとシャリが織りなすシンプルながら奥深い味わいは、多くの人々を魅了してきました。しかし、お寿司の楽しみ方やマナーには地域による違いや歴史的な背景があり、知れば知るほどその魅力が深まります。今回は、お寿司の食べ方やマナーについて、関東と関西の違いを中心に、ホテルニューオータニ大阪に入っている寿司店「乾山」、店長の田上由将さんに教えてもらいました。
寿司を美味しく食べる順番はある?

shutterstock
お寿司は、白身魚から大トロ、貝類まで、多彩なネタが楽しめる日本を代表する料理です。好きなものを好きな順番で食べるのもいいですが、「美味しく味わうための順番」はあるのでしょうか。そのコツを探ります。
◆味の薄いものから濃いものへ
お寿司を美味しく食べる基本は、味の薄いネタからスタートし、徐々に濃厚なものへと進むことです。
「最初は薄い味わいのものがいいでしょう。トロを最初に食べてしまうと、脂が多いので口の中に濃厚な風味が残ってしまいます。大トロのような脂の強いネタを最初に食べると、その後の繊細な味わいが感じにくくなるため、白身魚など淡泊なものから始めるのがおすすめです。
この流れは、フレンチのコース料理に似ています。メインにかけてだんだん値段が高いものを食べる感じです。具体的には、最初に白身魚、次にホタテやイカ、中盤にアジや光り物(鯖や鰯など)、そしてマグロ、ウニ、イクラ、エビといった高級ネタを後半に持ってくるのが一つの定番です」
◆江戸前寿司の伝統的な順番
「江戸前寿司では、さらに明確な順番があります。最後に絶対穴子を出します。関東では煮穴子が主流なのに対し、関西では焼き穴子が好まれるなど、地域差も見られます。また、最後に巻き物としてかんぴょう巻きを出すお店も。
最初と最後に出すのは店の一番の売り物。印象に残るからです。店のこだわりが感じられる瞬間です。中盤には、イカやホタテといった『王道のネタ』を配置し、バランスよく楽しめるよう工夫されています。この順番のポイントは、一つ一つのネタの味が分かりやすいことです。味の強弱を意識することで、それぞれのネタの個性が際立つのです」
◆自由に楽しむ現代のスタイル
「とはいえ、自分の食べたいものを好きな順番で食べても構いません。最近ではインバウンドの影響で海外からのお客様も増え、最初からウニやサーモンを食べる人もいます。お寿司は本来、屋台で気軽に楽しむ庶民の料理だったため、ルールに縛られすぎず自由に味わうのも正解です。寿司は、いろいろ好きなものを食べる料理なので、それでいいのです」
◆美味しく食べるためのコツ
お寿司を美味しく食べる順番に決まりはありませんが、伝統的な流れを知っておくと、より味わい深く楽しめます。以下は一つの目安です:
- 白身魚(ヒラメ、タイなど):淡泊で繊細な味わいからスタート。
- ホタテやイカ:少しコクのあるネタで中盤へ。
- 光り物(アジ、サバ):独特の風味でアクセント。
- マグロ、ウニ、イクラ、エビ:濃厚な味わいを後半に。
- 穴子や巻き物:締めとして印象的な一貫を。
もちろん、「今日はトロから食べたい!」という気分なら、それも大いにアリ。お寿司の魅力は、ルールを超えた自由さと、歴史に裏打ちされた伝統の両方を楽しめるところにあります。ぜひ自分なりの「美味しい順番」を見つけてみてください。
江戸時代の寿司と現代の違い

shutterstock
「寿司を屋台で食べていたというと驚くかもしれませんが、お寿司の歴史を振り返ると、江戸時代に屋台から始まった庶民の食べ物でした。当時は冷蔵庫がなく、トロのような脂の多いネタは存在せず、鯖や小肌のしめ物、茹でエビなど腐りにくいものが主流でした。マグロは赤身しかなかったそうです。たぶん氷の上にネタを乗せていたと思います。
また、当時のシャリは赤酢が使われていました。今も流行っていますが、美味しそうに見えるのでしょうね。現代でも赤酢が見直されています。しかし、関西では押し寿司文化が根強く、赤酢はあまり馴染みません。赤酢は味が濃い。関西の押し寿司はネタを塩漬けにすることが多いので、シャリの味もネタの味も濃くなりすぎてしまいます。関西のシャリは甘みが強く、関東は塩気が際立つなど、地域ごとの個性が際立っています」
◆ガリの地域差
「ガリ(生姜の甘酢漬け)にも地域差があります。関東では塩味が強いガリが一般的ですが、関西では砂糖を多めに使った甘めのガリが伝統的。関西の昔の寿司屋は全部紅生姜です。最近は関西の回転寿司でも関東風の白いガリが増えてきています。ガリは机に置いてある店もありますが、最近では置かないお店も増えています。うちでは衛生上、一皿ごとにガリを付けています」
◆お寿司と一緒にお茶を飲む理由
「お寿司屋さんに入ると、まず出されるのが緑茶です。これは単なる喉を潤すためだけのものではなく、口の中をさっぱりさせる役割があります。さらには、殺菌効果もあると言われており、特に生ものを扱うお寿司との相性が良いのです。お寿司を食べる前後に一口飲むことで、次の一貫をより美味しく味わえる効果もあります。わさびは風味を加えるだけでなく、殺菌作用もあるとされています」
◆お醤油のつけ方の流儀
お寿司を食べる際の醤油のつけ方は、人によってさまざまです。地域差が明確に現れるポイントでもあります。
- 関東の江戸前スタイル
「関東では、寿司職人がネタに醤油を塗って提供するのが一般的です。うちでは全部味付けして出します。それが江戸前なんです。シャリに醤油をつけると米が崩れてしまうため、ひっくり返してネタ側に軽くつけるのが正統派とされています。さらに、江戸前寿司では『手で食べる』のが基本。屋台文化から始まったこのスタイルは、手軽さとスピード感を重視しており、手でそのまま口に運ぶのが伝統です。おしぼりが用意されているのも、手で食べた後に指を拭くため。昔はのれんで手を拭いて帰るっていうのがあって、のれんが汚いほど流行っているって言われたんです」 - 関西スタイル
「一方、関西では自分で醤油をつけて食べるスタイルが主流です。関西は醤油を塗ってないんです。うちは江戸前ですから醤油を塗って出しますが、物足りない人のために醤油を置いています。お客が自由に味を調整するスタイルが好まれ、箸を使って食べる人も多いようです」
◆手で食べる?箸で食べる?
「できたら手で食べてもらった方がありがたいです。お箸で掴むと崩れるじゃないですか。今は柔らかく握っているので崩れやすいんです。ただし、手で食べるのが苦手な人には無理強いはしていません。
NGマナーと気を付けたいこと

shutterstock
◆醤油をべったり付けない
寿司は好きな順番で食べたらいいと寛容な田上さんですが、一つだけNG行為としてあげたのが、「醤油をべっちゃりつける」ことです。
「柔らかく握ってるんで、無茶苦茶になってしまうんです。シャリからネタを外してネタだけ食べる人も時折見かけるのですが、作った側としてはちょっと残念です」
お寿司はシャリとネタのバランスが命。両方を味わうのがマナーと言えるでしょう。
◆注文のタイミングと勘定の仕方
回転寿司ではなく、普通のカウンターで食べるお寿司は注文するタイミングに困ることも。忙しく働く職人さんにどのタイミングで声をかけたらいいのでしょう。
「普通に注文してくれたらいいですよ。お寿司屋さんによっては、『何かありますか?』と気軽に聞いてくれるところもたくさんあります。初めてでも緊張せず、気楽に楽しんでください」
◆お勘定をスマートに済ませるには
「会計時に『お愛想』と言うのは昔からタブーとされています。『お愛想』と言う方も結構いらっしゃいますが、『この店には愛想が尽きた、もう来ない』という意味が含まれているので使わない方がいいのです。普通に『会計をお願いします』や『ごちそうさまでした』と言う方が自然でスマートです」
お寿司を楽しむコツ
お寿司屋さんを選ぶコツは、「まず値段を見て、雰囲気を感じに一度行ってみる」こと。そして、関東風か関西風か、自分の好みに合ったスタイルを見つけるのも楽しみの一つです。伝統的な江戸前寿司の手軽さも、関西の自由な味わい方も、どちらもお寿司の多様性を象徴しています。ぜひ、次のお寿司屋さんでは、手で握りをつまんで、江戸前寿司を気軽に味わってみてください。
◆予約制の増加と現代の変化
コロナ禍をきっかけに、完全予約制の寿司店が増えた背景も興味深いです。
「お客さんがいつ来るかわからないから、仕入れても捨てるのがもったいない。そこで予約制にしてロスを減らすようになったんです。高級店はほとんどが予約制ですが、一見で予約を取るのはなかなか難しいでしょうね。常連さんが誰かを紹介していくので、それだけで席が埋まってしまいます」
ただ、予約サイトを活用している高級店もあるので、チャレンジしてみるのもいいですね。